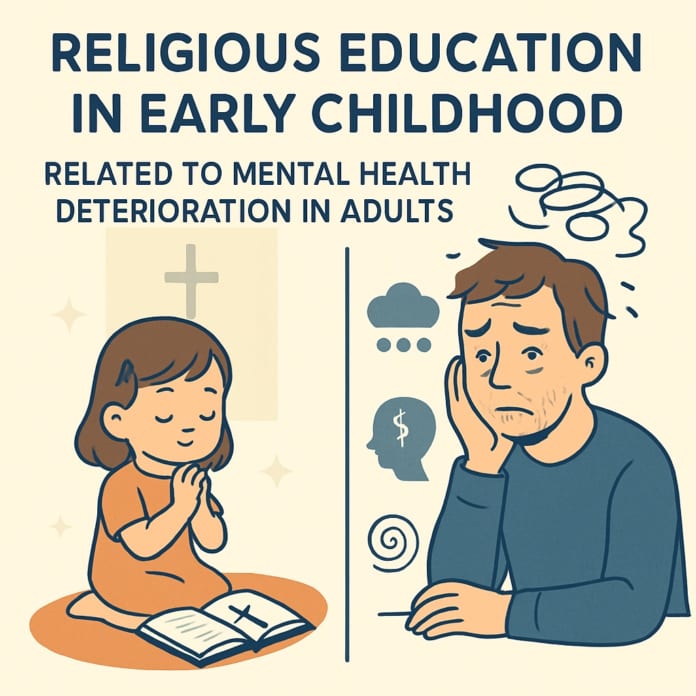「信仰は人生を豊かにする」――そう信じられている一方で、特定の宗教的背景を持つ家庭で育つことの困難さ、いわゆる「宗教2世」の問題が、日本でも深刻な社会問題として認識され始めています。
こうした中、ヨーロッパで行われた1万人規模の大規模調査が、幼少期の宗教教育と、成人後の健康状態との間に、複雑で「予期せぬ関連性」があることを示し、波紋を広げています。
この研究は、宗教が必ずしも心身の健康に良い影響ばかりを与えるわけではない可能性を、統計データによって浮き彫りにしました。
身体機能は「良好」、しかし精神と認知は「不調」という“ねじれ”
この研究は、50歳以上のヨーロッパ人10,000人以上のデータを分析。幼少期に親から宗教的な指導(信仰教育)を受けて育った人々が、そうでない人々と比べて、将来の健康状態にどのような違いが出るかを調査しました。
その結果は、単純に「良い」か「悪い」かで割り切れない、非常に“ねじれ”たものでした。
マイナス面(精神・認知): 宗教的な教育を受けて育った人々は、成人後、「うつ傾向」を測定するスコアが有意に高い(=メンタルヘルスが悪い)ことが判明しました。 さらに、計算能力や空間認識能力といった「認知機能」のテストにおいても、成績が低い傾向が見られました。
プラス面(身体): その一方で、「身体的な機能」に関しては、むしろ良好な結果を示しました。着替え、歩行、入浴といった「日常的な動作」において、困難を感じる(制限がある)と回答した人が少なかったのです。
この「身体は健康だが、心と認知は不調」という相反する結果は、研究者にとっても予想外のものでした。幼少期の宗教的なしつけが、身体的な規律(ルーティン)を育んだ可能性がある一方で、精神面や認知面では何らかの負担となっていた可能性が示唆されます。
最大の問題点―「困難な家庭」では、宗教が“救い”にならなかった
さらに深刻なのは、家庭環境との相互作用です。この研究は、宗教教育が「どのような家庭」で行われたかによって、その影響が全く異なることを突き止めました。
分析の結果、幼少期の宗教教育と、成人後の健康悪化(特に精神・認知面)との負の関連性は、「困難な家庭環境」で育った人々において、より一層強く現れたのです。
具体的には、親が精神疾患を抱えていた、親がアルコールに依存していた、といった問題を抱える家庭で宗教教育を受けていた場合、そうでない家庭で育った人よりも、成人後のメンタルヘルスや認知機能のスコアが、さらに悪化していました。
宗教は「緩衝材」ではなく「重荷」になった?
これは、一般的に期待されがちな「信仰が、困難な家庭環境の“救い”や“緩衝材”になる」という見方を否定するものです。
研究者らは、困難な家庭環境という逆境に、さらに宗教的な教育が上乗せされることで、それが支援となるどころか、「内面的な葛藤」や「精神的なプレッシャー」を強め、かえって長期的な健康を害する要因になったのではないか、と推測しています。
もちろん、この研究は「宗教が健康問題を引き起こす」という直接的な因果関係を証明するものではありません。
しかし、日本で問題となっている「宗教2世」の人々が訴える精神的な苦悩とも重なるように、幼少期の宗教的な環境が、特に困難を抱えた子供たちにとって、人生に長期的な影響を及ぼす「重荷」となり得る可能性を、大規模なデータで示した点で、非常に重要な研究と言えるでしょう。